2 AmberTools1.3 をバンドルする方向で検討中。antechamber と sqm だけあればいいはず。
4 config.h, Makefile_at を手動で修正。
5 src ディレクトリの中で、antechamber, blas, carpack, cblas, clapack, etc, f2c, include, lapack, lib, sff, sqm を残し、他は削除する。
7 make -f Makefile_at でビルド。
8 なお、Mac 用の gfortran は http://r.research.att.com/tools/ にあるやつがいい。hpc.sourceforge.net のやつはいろいろと使い方が複雑。
9 OS 10.4 用のユニバーサルバイナリは、export ISYSROOT='-isysroot /Developer/SDKs/MacOSX10.4u.sdk -mmacosx-version-min=10.4 -arch ppc -arch i386' としたあと make -f Makefile_at とすると作ることができる。MacBook 上でビルドして、PowerPC の 10.4 に持って行っても実行できたので、たぶん大丈夫じゃないかと。
10 原子タイプのアサインだけなら、antechamber を -c オプション無しで走らせればいいんだな。気がついてなかった。(どれぐらい使えるのかは不明だが。)
13 MD/Minimize のサブスレッドの処理を整理(よくフリーズしていたので)。
14 サブスレッドから MM/MD をしているときは、指定したステップが終わるごとにリングバッファに座標データをためこみ、メインスレッドにイベントを投げる。メインスレッドはイベントを捕まえて、リングバッファから座標データを読み込んで、フレームを作成する。サブスレッドから Molecule を直接触ることがなくなったので、少しは安定すると期待しよう。また、ドキュメントを閉じるときにサブスレッドが走っている時は、エラーメッセージを出して閉じるのを拒否するようにした。
17 Ruby の Parameter/ParEnumerable の仕様がわかりにくい。グローバルパラメータを自動的に探しに行く機能はlookup メソッドに限定する。Parameter#lookup(par_type, atom_type_string, *options), ParEnumerable#lookup(atom_type_string, *options).
18 Parameter#bond, ParEnumerable#[] などで、原子タイプからの探索はやめにする。また、ローカルな Parameter の nbonds などがグローバルパラメータを含んだ値を返すのはやめる。
19 Parameter#bond などをクラスメソッド・インスタンスメソッドとして二重に登録するのはやめた。グローバルパラメータはたとえば Parameter.builtin.atoms または Parameter::Builtin.atoms としてアクセスする。
22 Parameter タイプの atom というのはなんとも紛らわしい。element の方がまだましかも。
25 RubyDialog って名前はよくないな。Ruby のクラス名に "Ruby" って接頭辞をつけてどうすんだよ。全体を Molby というモジュールにして、暗黙に include Molby することにしようか。これなら、RubyDialog は Dialog でもいい。
26 DialogItem を独立したクラスにしたいんだけど、オーナーシップをどうしようか?
27 DialogItem は常に Dialog#item で作成されるので、このとき作ったオブジェクトを Dialog._items に格納し、常にそれを返す。従って、Dialog#get_item(n) で返されるオブジェクトは常に同一。
28 DialogItem は Dialog へのポインタとアイテム番号を保持すべき。アイテム番号はともかく、ポインタはどう保持するか? Dialog._items -> DialogItem -> Dialog という循環参照を作っても、Ruby の GC ならちゃんと回収してくれるから、これでいいんじゃないか。他のいい方法が思いつかん。
29 DialogItem は C レベルのデータは持たず、単なる cDialogItem のインスタンスとする。属性は、今まで Dialog 中のハッシュに保持していたが、DialogItem のインスタンス変数として実装する。
30 Dialog#item(:type, hash) でアイテムを作成。Dialog#set_attr, Dialog#get_attr はやめて、DialogItem#[], DialogItem#[]= で実装する。DialogItem#属性名, DialogItem#属性名= も実装する(ParameterRef と同様)。また、Dialog#action の引数はアイテム番号でなく DialogItem オブジェクトとする。
31 DialogItem の action 属性は今までと同様だが、引数としてはアイテム番号でなく DialogItem オブジェクトそのものが渡される。
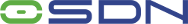 OSDN Git Service
OSDN Git Service