-Feeding Origin 2 は、日本飼養標準に基づいた家畜の養分要求量の計算および飼料設計を支援するソフトウェアです.
+FeedingOrigin2
+
+ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(略称:農研機構)で制作された日本
+飼養標準・乳牛(2006年版)(中央畜産会発行、ISBN:4901311441、
+https://www.naro.affrc.go.jp/nilgs/contents/shiryo_hyojyun/nyugyu2006/index.html)
+に準拠し、家畜(乳牛)の養分要求量の計算を支援するソフトウェアです。
+
+
+【プロジェクトの説明】
+
+ 日本飼養標準には養分要求量の計算方法が記載され、実行形式のプログラムのjfs_d08
+ が公表されています。しかし、本に記載された数式でプログラムを制作しても、jfs_d08
+ で算出される数値とは一致しません。農研機構の関係者に尋ねると、本書の内容とjfs_d08
+ の数式は異なるのだそうです。が、ソースコードは公表しないということでした。作者は
+ たいへん困惑したのですが、本書の問題を洗い出し、jfs_d08と変わらない値を出力する
+ プログラムを作成しました。
+ FeedingOrigin2は作者がスクラッチから制作した独自のものです。
+ 下記に関連するWebサイトを記します。
+
+ jfs_d08.lzh
+ https://www.naro.affrc.go.jp/nilgs/contents/shiryo_hyojyun/nyugyu2006/jfs_d08.html
+
+ 乳用牛養分要求量計算プログラム(Origin)の製作経緯と留意情報
+ http://www.ccppro.com/agri/feedcalc/Origin2011A004_3.html
+
+ 近年、日本の酪農家が激減していると伝えられますが、少しでも酪農業の発展に役立
+ てば幸いです。
+
+
+【プログラミング環境】
+
+ 言語/開発環境:FreePascal/Lazarua
+ http://www.lazarus-ide.org/
+
+ OS:Windows、Linux(DOS/V)
+
+
+【リポジトリ(Git)の内容】
+
+ ・Documents
+ 説明文など
+
+ ・NichiZotaijyu
+ 日本飼養標準(2006年版)の基礎となっている成長曲線に基づき、日齢に対する体重
+ および体重に対して1日の増体重を計算するプログラムです。
+
+ ・HikakuBunseki
+ FeedingOrigin2と農研機構から公開されているjfs_d08について、育成牛の養分要求量
+ の算出結果を比較するプログラムです。
+ 本プログラムは両方の値をグラフ表示し、その違いを検討できます。また、修正指数曲線
+ で回帰分析し、グラフに表示します。階段状になる要求量を滑らかな曲線で平準化する
+ 方法を提議します。
+
+ ・Youkyuryo
+ 日本飼養標準(2006年版)に準拠し、搾乳中の乳牛、乾乳牛そして育成牛の養分要求量
+ を計算します。
+
+
+【ライセンス】
+
+ FeedingOrigin2のライセンスはGPL3で公開します。GPL3の内容は本来は英文で記述され
+ ていますが、日本で公開することを踏まえて、八田真行氏が翻訳したものを参照すること
+ をお勧めします。https://mag.osdn.jp/07/09/02/130237
+
+
+
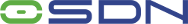 OSDN Git Service
OSDN Git Service